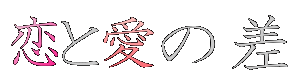
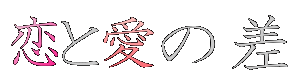
1.それはほんの少しの気持ちの違和感
ガキの頃、意味も分からず母さんに聞いたことがあった、恋と愛の違いは何かと、
すると母さんは笑って答えてくれた。
「恋はね、自分だけの気持ちで成立するものなの、恋し合うとは言わないでしょ?
だから、新ちゃんが誰かを好きになって、例え相手に好きになってもらえなくてもそれは恋として成立するの、
だけど愛はふたりの気持ちが同じでなければ成立しないわ、
愛し合うって言葉通りお互いがお互いを思い合わないとそれは愛にならないの……って、
流石にこれは難しすぎたかな?新ちゃんももう少し大人になったらわかるわよ」
そう言って、俺の頭を撫でた母さんの言葉の意味を俺が本当の意味で知ることになったのはそれから10年経ってからだった。
俺は幼馴染の毛利蘭に恋心を抱いていた、そうこの気持ちはやがては愛に変わるものだと思って疑っていなかった。
だが、成り行きとは言えロンドンで蘭に告白をして三ヶ月が過ぎた頃、俺は徐々に自分の恋心が冷めていくのを否定できなかった。
理由は、告白の返事を蘭が一切返してこなかったからだ……。
最初はいきなり過ぎる告白に戸惑ったのと、両思いだという嬉しさ、あとは照れ隠しもあるのだと想い俺は何も返事を催促する言葉を口にしなかった、
が、たまにかかってくる電話はいつものように語気が荒く、
「いつになったら帰ってくるのよ!」や「事件事件ってそんなに事件が大事なの!?」など自分に対しての苦情ばかり、
待たせている、帰れない、事情を話せないという後ろめたい気持ちがあった俺は、言葉を濁して謝ることしかできずにいた……。
だが、それでも告白の返事をしない理由にはならないと思い始めたのは、偶然聞いた園子のある一言がきっかけだった、
告白から一カ月ぐらいたったある日、放課後学校から帰っていると、偶然にも俺は園子と蘭が話しているのを聞いてしまう。
「蘭、新一くんに告白の返事したの?」
「ううん?まだしてないけど、だってあいつ事件事件で帰ってこないし……」
「そうだけど、蘭、いい加減に電話でもメールでもいいから告白の返事しなさいよ、
新一くんに告白されてからもう一ヶ月近く経ってるんだよ?」
「そうだけど、こっちはこっちで帰りをずっと待たされてるんだよ?新一だって返事聞きたいなら帰ってきて顔見せに来たっていいじゃない!」
「それを蘭は新一くんに言ったわけ?告白の返事したいから一度帰ってきてほしいって」
「言ってないわよ」
「じゃあ新一くんだって、事件を遊びで追ってるんじゃないんだから帰ってくるわけないでしょ何の用事もないのに」
「私に会いに来るのが理由がないと来れないっていうの?!」
「そうじゃなくて、なんでも物事には優先順位ってものがあるでしょ?
蘭、事件捜査が大変なのはおじ様の仕事が忙しくなった時にどんなものかわかってるはずよ、
新一くんはおじ様とは申し訳ないけど探偵として能力は格段に違うわ、そもそも探偵としてのタイプが違っていたじゃない、
それに、事件になると蘭のことそっちのけになるのは行方知れずになる前からそうだったでしょ?」
「でも、あの時は次の日になれば新一に会えたし、いつだって会えたから……」
「だったら、状況が変わったのなら、相手との接し方も変えていかないといけないのは当たり前なんじゃないの?」
尚もうだつが上がらない態度の蘭に、園子ははっきり言った。
「……蘭、あんた本当に新一くんのこと好きなの?私だったら告白してくれた時点で返事してる、
私もずっと新一のこと好きだったって、蘭、告白の返事をしないってことは、新一くんの気持ちが離れていってもおかしくないってことわかってるの?」
「新一が私に好きって言ってくれたのよ?それなのに離れていくなんてあるわけないじゃない」
「蘭、とにかく早く返事しなさい、新一くんのことを本当に好きならなおさらね!」
「わかってるわよ、だから新一が帰ってきてから言うって言ってるじゃない」
「……私は忠告したわよ、蘭、これ以上は蘭の気持ちがあるだろうからもう言わないわ、
でも、蘭の気持ち、新一くんにはまだ一切伝わってないってこと、もう少しわかったほうがいいわよ」
と、そんな会話を、偶然俺は耳にしてしまった。確かに思っていた。
蘭を待たせてしまっている罪悪感から返事をもらえていない事実に目を背けていたが、帰りを待つのと告白の返事を待つのじゃ意味が違うのではないかと思い始めた。
それから数日たって蘭に連絡を入れると、いつもどおり、いつ帰ってくるのか、早く帰って来いといういつもどおりの小言を聞かされた俺は、正直言って蘭が俺を好きだというのは、
ただ単に恋に恋するようなもので、その先の関係が見えていないのではないかという思いが浮かんでいた。
そして、蘭にとっての俺の存在は別に愛に変わらなくても恋のままでもかまわない存在ではないのかと思うようになった。
そんな風に日常が過ぎていく中で、阿笠博士の家に来ていた俺はふと灰原に言った。
「……灰原、おめぇ、あの事件でぼろぼろになったジャケット、もう着れねぇだろ、お礼もかねて俺に新しいの買わせてくれよ」
「どういう風の吹き回し?今まで結構似たようなことあったけど、あなたそんな事言ったことなかったじゃない」
「今までの事全部ひっくるめてお礼がしたいんだよ、おめぇにはいつも助けてもらってるしな、正直、いつも助かってるって思ってんだ」
「……工藤くん熱でもあるの?何か悪いものでも食べたのかしら?それとも解毒剤の試作品でもほしいの?」
「バァロー!んなんじゃねぇよ、けど、おめぇと事件かかわるようになってからいつもお前には裏で助けてもらってばかりだと思ってよ、それに……」
「それに?」
「ちょっと、聞いてほしい事があるんだ、博士がいねぇとこでな」
「……わかったわ、じゃ、出かけましょうか」
「おう」
そういって出かける準備をし、俺と灰原は出かけた。
近くのデパートに来た、俺と灰原はまずジャケットを買うためにショップを見て回る。
「よさそうのあったか?」
「……」
そういって声をかけるも、返事をしない灰原に俺が視線をやると、
ブライダルショップのウェディングドレスの前であいつはそれを見上げ見つめていた。
少し見つめた後、苦笑して灰原は、「なかなか良いのないわね、他いきましょ」と別のショップを見て回るよう告げてくる。俺は瞬間的にあいつが何を思ったのかわかってしまった。
あいつ自身の過去を振り返って、自分にはこんな白いウェディングドレスは似合わないなどと思っているのだと、
いつからだろう、最初は感情なんて表情に出さなくて、何を考えているかわからなかったあいつの事が今は何を思っているか顔の表情だけでわかるようになったのは、
最初は組織の人間として出会い、俺の頭の中には疑いの感情しかなかった。
だが、彼女の姉、宮野明美の事を知り、あいつの過去をだんだん知ってくにつれて、強がってるあいつをそばで見続ける事によって、
守ってやらなきゃいけねぇ、こいつを安心して普通の生活送らせてやりてぇって思うようになっていた。それに、一緒にかかわる事件に関してもそうだった、
服部や俺の専門外、医療や薬学の知識に関しては灰原は俺たち以上の知識量と、いつもは慎重なくせに、いざって時は俺と同じくらいの行動力を見せる大胆さに、
俺は少しずつ灰原哀、いや宮野志保という女に惹かれている部分があるのかもしれないと思って一回自分の思考を止めた、
(おい、おい、俺今何思った?あいつの事を少なからず女としてみてるってことか?いやいや、相棒として頼りになる事をちょっと気になるって勘違いしてるだけじゃねぇのか?)
と思い直して、また思考を開始する。
「ちょっと、ジャケット見に行くんでしょ?」
声をかけられ、思い直そうとしていた思考をいったん止め、灰原に目を向ける、
「わりぃわりぃ、んじゃ、別の店行ってみっか」
「まったく、あなたの悪い癖ね、考え込むと周りが見えなくなるところ」
「わりぃな、お、この店なんかいんじゃねぇか?」
そういって、店に入ってみる。
ジャケットを物色している灰原を横目に、俺はウィンドウケースに飾られた、紫紺色のドレスコードに目が留まった。
そして、ふっと頭によぎったのは、18歳の姿に戻ったあいつがこれを着た姿だった。
(あいつが着たらこれ、似合うんじゃねぇかな……きっと)
と、不意に思った俺は、携帯を取り出し、その店のサイトを見て同じドレスをネットでオーダーしていた。このとき俺は何でこんな事がすぐにできたのだろうと思ったが、
そのときには、彼女、宮野志保を少なからず女性として意識していると思っていたのかもしれない、と、後に思い返す事になる。
「いいのあったか?」
「えぇ、今度は少し頑丈な生地にするわ、またいつ着れなくなるかわからないけどね」
「もしそうなったら、また俺が買ってやるよ、おめぇは大事な相棒だし、俺のせいでそうなること多いんだしな」
「……あなた本当に今日はどうかしたの?」
「いや、それより、少しどっかで飯でも食おうぜ、話もあるし」
「そういえば、話があるって言ってたわね、いいわよ」
そういって、俺は、デパートから出ると、俺が工藤新一だったとき、よく一人でコーヒーを飲みに行った喫茶店へ灰原を連れて行く、ここにつれてきたのは灰原が初めてだった。
偶然見つけたその店は、マスターがシャーロキアンだった事もあり、ホームズのアパートの内装に似せてあり、
人があまり入らないため、静かに小説を読みたいときなどに利用していた。灰原と一緒に店に入ると灰原は店の内装を見ただけでこういった。
「なるほどね、シャーロキアンにはここは至福の場所って所かしら?」
「まぁな」
やっぱり、わかっちまうんだな、と少しうれしくなって笑って店内に入ると、店の死角になる奥の席に座る。
「なんにする?」
「あなたにお任せするわ、あなたの行き着けなんでしょ?」
「おう、じゃちょっと注文してくるな」
そういって、俺はカウンターに行くと、マスターに注文し席に戻る。
「それで?」
「?」
「話って何かしら?」
「あぁ、その……おめぇにこんな事相談するのはどうなのかって思ったんだが、ロンドンでの告白の返事まだもらってねぇんだよ、蘭から……」
「あれからもう、3ヶ月は過ぎてるわよね」
「あぁ、んでさ、この間蘭と園子が話してるのを偶然聞いちまったんだ」
俺は、蘭と園子の会話をそのまま灰原に伝えた。黙って聞いてくれていた灰原の表情が少し曇る、話していて思った。
(灰原おめぇ、それはどっちの感情なんだよ、俺をコナンにしちまった事への罪悪感か?それとも、返事をしない蘭への不満か?)
「それで?あなたはどうしたいの?告白をなかったことにしたいとでも言うの?」
「正直、俺はあいつを待たせてるって負い目があったし、だから返事が多少遅くてもしかたねぇってあきらめてた部分があるのは確かだ、けどな、
俺はあの時俺なりに一生懸命気持ちを伝えたんだ、けど、あいつは俺の見せた誠意にあの言葉はないと思った、正直いって元に戻っても蘭とうまくやってく自信がねぇ」
「工藤くん……」
「おめぇは、俺と蘭が一緒にいるべきだと思ってるんだろうけど、俺は一緒にいるべきじゃねぇと思い始めてる、コンドウの事件のときもそうだ、あいつは失踪したコナンよりも、
自分のところに顔を見せない新一への怒りのほうが大きかった、怒りでおっちゃんの飯も作らなかったらしいぜ?」
「あくまで貴方に自分を優先してほしいってことなのね、貴方はいつだって彼女のためを思って行動してるっていうのに……
貴方を傷つけたくなくて言いたくなかったけど、正直コンドウでの事件、彼女に対して不信と怒りを覚えたのは確かよ、普通江戸川くんだったら工藤くんのことを知り合いのお兄ちゃんとは言わないし、
そのメールが工藤くんから送られてくる事もおかしいって思わないのかってね」
「灰原……ありがとな、怒ってくれて、ガキのころ母さんに聞いた事があった、恋と愛の違いは何かって、母さんは言った、恋は一人でもできる、
でも愛はお互いが同じ思いで思いあっていないと成り立たないものだってな、あの時は意味がわかんなかったけど、今は少しわかる気がするんだ、
あいつはきっと俺との恋に恋してるだけで、俺自身の気持ちはどうでもいいのかも知れねぇってな……」
「工藤くん……」
「あのさ、灰原、俺、組織をつぶすまで蘭と連絡絶ってみるよ、自分の気持ち見つめなおしてみる」
「そう」
「ありがとな、聞いてくれて、こんな愚痴、博士にも親父たちにも、ましてや服部になんて話せなくってよ、」
「良いわよ、別に弱音くらいはいたって良いじゃない、私たちまだ未成年の高校生よ?」
「そうだな、サンキュ!」
話がひと段落下ところに、オリジナルブレンドのブラックコーヒーとホットサンドが運ばれてくる、
「さ、食べようぜ?ここのホットサンドはサイコーにうめぇんだ!」
「えぇ、このコーヒーもいい香りね」
「あ、あとよ、久々にここで小説読んでいきてぇんだけどいいか?」
「良いわよ、私も気になる本が何冊かあったし、一緒に読んでいくわ」
「おう」
そういって、やさしく微笑む灰原に俺は蘭と一緒にいるときとは違う別の気持ちが生まれ始めていたことに気づくのはもう少し後になってからだった。


++あとがきと書いて反省文と読みます++
コ哀小説です、結城は蘭ちゃんが嫌いではないんですが、
新一の相手としては、力量不足という部分をすごく感じています。
哀ちゃんを見るたびに、コナン(新一)との関係性が蘭ちゃんとは違いすぎるなと感じます。
蘭ちゃんが金田一少年の美雪のような博学な子なら良かったんでしょうが、
そうなると作品が似てしまうからそういう設定できないのではと思いますが、
探偵の幼馴染という立ち位置だとあまりにも直情的かつ短慮な部分があるような感じがしています。今年映画20周年という長期連載になる作品であるからこそ、
この違和感は如実に現れていると思います。
その違和感を解消したくて自分の妄想を書いてみました。
この作品は今後は新一×志保になる予定です。よろしくお願いします。